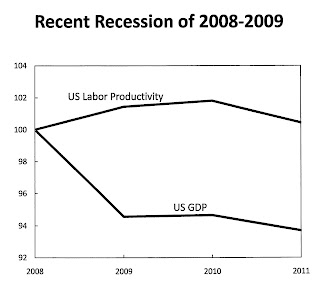上の二つのグラフは、政策金利(FFR)が1%引き上げられたとき(緊縮的金融政策)にジニ係数がどのように動くかを示している。X軸は四半期単位である。右側が賃金収入、左側が税引き後の総収入である。左側の総収入を見ると、政策金利が1%引き上げられたときには総収入のジニ係数が最初は少し下がるものの長期的には約1/4%動くことを示している。
但し、ジニ係数だけ見ても、それぞれの個々人の収入がどのように動いたかを見るのは難しいので次のグラフも示しておく。上のグラフは、左側で言えば、総収入が下から数えて10%の人と、25%の人、50%の人(メディアンである)、75%の人、90%の人の総収入が、政策金利が1%上がったときに(緊縮的金融政策)どのように動くかを示している。
では賃金収入(右側)から見ていこう。金利引き上げの短期的な(最初の2年)影響はなんともいえないが、長期的な影響は少しジニ係数を引き上げる、つまり、不平等を助長する方向に影響を与えているようだ。更に、内訳を見ると、賃金収入で上から25-50%の人の収入にはほとんど影響はないものの、下から10-25%の人の賃金収入は1-2%程度下がっている。反対に、上位10%の人の賃金収入は1%程度増えている。背後にあるのはなんだろう?容易に考え付くのは、賃金が低めの人は金利の引き上げに伴って失業のリスクが高まり、賃金収入が減るというものであるが、筆者らは、フルタイムの労働者に限っても同じような結果が得られるといっているので、高賃金労働者と低賃金労働者の間には、金利が動いたときの賃金の反応に非対称性があるようだ(これ以上の深い分析はなされていない)。
では、総収入(左側)はどうか?さっき書いたとおり、金利が1%引き上げられたときには ジニ係数が最初は下がった後で長期的には1/4%上昇することが上のグラフから見て取れる。また、総収入の異なる人の収入の変化の大きさは、賃金所得の変化の大きさより小さい。特に、総所得で見て下位10-25%の人の所得の減り方がとても小さい。筆者らはこれを、失業保険等の社会保障制度が有効に機能しているおかげだと述べている。一方、高所得者の総収入は賃金収入と同じく長期的には1%程度増えることとなっている。これだけ見ると、ジニ係数の動きは賃金収入より小さそうなものであるが、なぜかジニ係数の動きはは大きくなっている。考えられる理由の一つは高所得者(上位10%以上)の総収入が大きく増えるということか。
では消費サイドを見ていこう。
上のグラフは再びジニ係数の動きを示している。右側が(狭義の)消費、左側が総支出(=消費+車の購入+住宅ローンの支払い+教育関連支出+医療関連支出)である。消費の水準を下から見て10%の人と、25%の人、50%の人(メディアンである)、75%の人、90%の人の消費の動きを示したのが下のグラフである。
では狭義の消費(右側)から見ていこう。ジニ係数で見ると金利引き上げ時の動きは小さい。これは所得の動きの少なくとも一部が一時的なものであることからかんがみて、納得のいく動きである(恒常所得仮説だ)。ただ、内訳を見ると、ぜんぜん印象がちがう。消費のレベルが引く人たちの消費は1-2%落ち込む一方、消費水準の高い人たちの消費は0-1.5%程度上がる。
さらに解釈が難しいのは、広義の消費(左側)である。ジニ係数は大きく上昇する。政策金利が1%上昇
したときには長期的にはジニ係数が0.7%程度上がることが見て取れる。さらに、それぞれの消費レベルの異なる人の総消費の動きを見ると、上位10%の人の消費は5%程度増える一方、下位10%の人の総消費は2%程度落ち込む。これはかなり大きい動きである。金利が上がったときに車を買ったり、住宅ローンの支払いが増えたりしているであろうが、今ひとつ解釈がよくわからないところである。
全体的にいえるのは、インパルスレスポンスによると、金融政策の変更によっていろいろな面の不平等が大きく影響を受けるということである。特に、金融政策の引き締めはさまざまな不平等の拡大と相関している。但し、どのようなメカニズムによってデータで見られる変化がおきているのかはこのデータを見ただけではよくわからないというのが感想である。
それに、重要なのは、財政政策に何が起こっているか、「金融政策ショック」をどこまで 外生的なものと捕らえられるかであろう。個人的にはぜんぜん外生とは考えられない気がするが、それでも、このように将来のモデル構築の際に役立つデータを提供してくれるのは重要な貢献である。ゼロ金利制約に経済が引っかかっている状況で金融政策の影響がどう異なるかにも興味があるが、データが足りないだろう。